- TALK SESSION
- #01
-
大学院×大学×高専 出身者
各学校で学んだことがアステックでどう活かせているか
大学院、大学、高専(高等専門学校)と、それぞれ学歴の異なる若手3名によるトークセッション。
アステックを選んだ理由や現在の業務内容、各学校で学んだことがどう活かせているかなど、自由に語り合ってもらいました。
- メンバーMEMBER
-
 2021年4月入社
システム開発カンパニー
2021年4月入社
システム開発カンパニー
新規事業推進部
ソリューション開発一課 福澤 航大 (大学院 工学研究科 情報電子工学系専攻 出身) -
 2024年4月入社
システム開発カンパニー
2024年4月入社
システム開発カンパニー
新規事業推進部
ソリューション開発一課 松崎 翼 (大学 理工学部 システム理化学科 出身) -
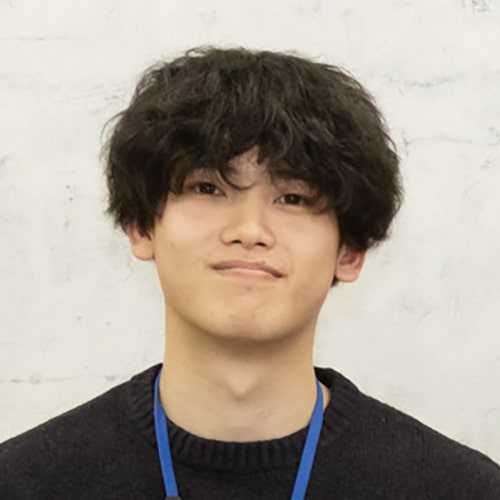 2024年4月入社
システム開発カンパニー
2024年4月入社
システム開発カンパニー
制御システム開発部
開発二課 山中 陽仁 (高専本科 電子制御工学科 出身)
Q:業務の内容や仕事のやりがいは?

私と松崎さんは同じ部署だけど、業務上で直接指導したことは、今のところ一度もないよね。

まだ同じチームになったことがないですもんね。でも道具の使い方とか日報の書き方とか、社内のことは結構、福澤さんに教えてもらって感謝しています。

それぞれどういう仕事を手がけているんですか?

今はクラウド環境の構築を取り扱うことが多いかな。私の業務は多岐にわたっていて、1~2カ月スパンで違う仕事に入ったり、最近だと他部署支援という形で、機械制御の仕事にも携わったり。いろんなノウハウを学べる機会があってありがたい。挑戦してみたい分野を伝えて、その案件に携わらせてもらえることが多いので、すごく満足して仕事ができているなと。

私は現在、鉄道の路線状況など、インフラ関連のデータを深く見るためのツールをつくっています。たとえば駅に設置する端末に、機器が正しく作動しているかを見るための機能を追加したりだとか。まだ1年足らずですが、かなり多彩に手がけられ、すごく楽しいです。できることが着実に増えて、やりがいがありますね。

うちの部署は、3~4人くらいの小さいチームで業務を回していくことが多くて。私の場合だと、管理役の上司が1人ついて、実作業は1人で行うケースも多いし。だから同じ課でも、一緒になることが結構ないんだよね。本社以外も含めると制御系の方が大人数でやるプロジェクトが多いイメージだけど、山中さんのところは?

私のところは小規模で、現状、実務は指導の先輩と2人で担っています。工場で使われている機械の基盤に対して、アプリケーションの機能拡張だったり、その型番にはない機種の機能を移植したりといった作業を。成果を実感しやすくて面白いです。

部署によっては、大規模なチームで大きな開発プロジェクトを回す業務に携わっている人たちもいるけど、それはそれでまた違った達成感があって楽しそうだよね。

Q:各学校の専攻を選んだ理由や入社の動機は?

私は高専に進みたいと思ったのがすごく早くて、小学4年生のときだったんですよ。

早い!小学生の頃なんて、高専の存在すら知らなかったのに…。

(笑)夏休みにあった奈良高専主催の体験教室に参加して、ロボットを組み立てたのが楽しかったんですよね。とはいえ将来の目標までは決めかねていたので、幅広く学べる学科を選びました。

私はもともとゲームの開発が趣味で、システム開発の道に進めればと地元北海道の室工(室蘭工業大学)に進学したんだけど。高校時代まではゲーム開発にゲームソフト(ツクール系)やスマホアプリを使っていて、実はパソコンを本格的に触り始めたのは大学に入ってからなんだよね。

意外ですね。自分は小さい頃からパソコンを使うのが好きだったから、プログラミングをやってみたいなと情報系の学科へ。就職は、大学へ説明会に来てくださっていたIT系の企業から選ぼうと考えていました。それで5社ぐらいの話を聴いて、面白そうだなと感じたのがアステックです。福澤さんをはじめ、同じ大学の先輩がいることは、入ってから知ってびっくりしました。

実は、私と私の同期1人が、室工からの初入社なんだよね。そこから開拓が始まったという(笑)。ソフトウェアに特化した仕事をやりたいと考えていたので、アステックならそれが幅広く実現できそうだと感じたのも大きかったな。

私は高専で毎年行われていたロボットコンテストを通じて、組込系のソフトウェア開発をやってみたいなと思ったのがきっかけです。当時は機構の製作を担当していたので、自分もできるようになりたいなと。アステックは校内の説明会で知り、希望を汲んでもらえる印象を受けたんですよねOBの先輩もかなり多く、見学会でもお話しさせてもらう機会があって、ほぼ即決のような形で志望しました。ただ、出身の学科からは、私が初めてだったみたいです。

開拓者だ!

(笑) 私は地元の関西圏がいいなと思っていたんですけど、北海道から大阪を選ばれたのは…?

私は出身が長野なんですけど、出かけるのが好きだし、せっかくなら知らないところ住んでみたいなと考えていて。首都圏は親戚がいて何度も行ったことがあったので、大阪本社を志望したんですよ。まだ1年も経っていないのに、近畿だけでなく北陸や九州も含めて結構いろいろ回りましたね。

斬新な理由!私は大阪本社を訪問したときに説明された業務が、面白そうなシステム開発だったので希望を出したって感じ。だけど実は、近くに住みたい人が大阪にいたっていうのも大きな理由…っていうのは内緒の話で!


(笑)

Q:各学校で学んだことがどう活かせている?

新入社員研修のうち、最初の1カ月間は、ビジネスマナーなど社会人としての基礎的な研修を受けたんだけど、私の場合、残り2カ月間はスキップして、すぐOJTに入ったんだよね。入社時点でUnityでのゲーム開発経験があると伝えていたので、それなら早速業務に入った方が身になるだろうと判断されて。そういう先輩たちも結構いるので、柔軟に対応してもらえる会社だなと。

できる人ならすぐに業務に入れるのもいいですね。私はソフトウェアを学ぶ学科でもなかったので、研修から頑張っていこうと考えていたんですけど、卒業研究では、音声認識を使った楽曲制作のソフト開発を手がけていて、Pythonの知識は一から習得したんですよ。現状、実務で使っている言語とは異なるものの、その素養があった分、理解しやすかったと思います。

研修のとき2人に交流はあったの?

コースが3つあって、私がJavaコースで山中さんがC言語組込コースだったから、ガッツリ関わる感じではなかったですね。大学の卒業研究は画像解析AIで、写真をもとに医療器具を判別するパターンマッチングのウェブアプリケーションを開発しました。現状、画像系の案件はないですが、そのときのツールや言語の基本的な使い方が、今の業務にも活かせています。

画像認識系の業務は私も経験したことがあるので、今後もまた出てくると思うよ。AI関連の業務も今、ソリューション開発三課が技術面の研究にも取り組んでいるし、今後どんどん動いていくんじゃないかな。私も大学院ではAIの強化学習に特化した研究を行っていたんだけど、これまでに手がけた業務で、研究に使ったツールを活用する機会もあったし、当時勉強したAI関連の基礎的な素養は大いに役立っているなと。

学生時代の経験が活かせる場面は随所にありますが、研修にはプログラミング未経験の人も結構いましたし、何かしらの言語を使える段階にまでステップアップできる研修にはなっているから、初心者の人にも安心してほしいですね。

そうそう。アステックの場合、先輩方に相談もしやすいし。一人で業務ができるようになるまで、手厚く面倒も見てもらえるから心配は要らないと思います。

Q:今後の目標は?

今は目の前の仕事に必死ですけど、経験を重ねて、何かと任せてもらえる人間になっていきたいですね。これからは後輩が入ってくるので頼られる先輩になりたいし、上司から頼られる後輩でありたい。社会人としてもエンジニアとしても、自信をもてるように成長していきたいです。

エンジニアとして成長するか管理職として成長するか、アステックには大きく2パターンのルートがあるけど、最初のうちは自分の業務に専念して頑張ろう、という意識でいいんじゃないかな。どちらに素養があるかは、やっていくなかで見えてくるだろうし。かくいう私自身、どっちの軸かはまだ決めかねているんだけど。ただ、部署の先輩2人が、会社への貢献度を示すアステック賞のなかでも、最も優秀な金賞を受賞されているので、私もそこに続きたいなと。

毎年秋に行われる全体会議のときに表彰されるの、憧れますよね。

1人はエンジニア、もう1人はリーダーとしての強みを持っている人なので、自分も何か見いだしたいと思っている。目下のところではスマートフォン、とくにiPhone系の開発に関しては私が道を切り開きつつあるので、突き進んでいけたらなと。

私も期待に応えられるような人間になりたいですね。それこそ福澤さんみたいに頼もしく、活躍できるように成長していきたいです。今は上司から指示を受ける側ですが、次第に主導権がこちらに来るでしょうから、うまくプロジェクトを回せるようにもしていきたいですね。

Q:就職活動中の方へのメッセージを!

同じIT系でも、仕事の形態によってずいぶん違います。アステックは受託系だから、入ってくる案件に応じて業務内容もかなり変わってくる。いろいろ挑戦してみたい人には、もってこいの環境だと思いますよ。私自身、就活では自社開発をされている大きな会社さんにも行ったんですが、業績ベースでやれることが決まっている感じだったから、自分にはアステックのほうが向いていましたし。

幅広い仕事を経験できるおかげで、さまざまなスキルが身につくと思います。近しい案件をやり続ける企業さんも、一つのことを深く掘り下げられるメリットがあるでしょうけど、まず広く知れるというのは、とてもありがたいです。

どうしても実務って、やってみないとわからない部分も大きいですからね。やる前から決めすぎないで、飛び込んだり挑戦したりする勇気をもってほしいなと思います。

業務内容はもちろん、社内環境なども見比べて、自分に合ったところを選んでいくのが一番ですよね。

オフィス内もリニューアルされましたけど、アステックの場合、私たちの働く環境をとても大事に考えてくれ、積極的により良くしてくれているのが嬉しいですよね。モチベーションにもつながるじゃないですか。「自分たちのことを思ってくれている」という気持ちが伝わってきます。

社員ベースで考えてくれる風土はあるよね。社内環境だけでなく、業務内容への要望も聞いてもらいやすい。ものすごく風通しがいいし、そのあたりも離職率の低さにつながっているんじゃないかな。

まずは幅広く、いろんな情報を見るのが大事だと思うので、業界研究や企業研究に励んでほしいです。そして見比べてもらったうえで、選んでもらえると嬉しいですね。


